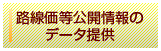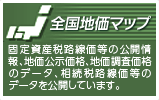|
トップ > 事業紹介 > 評価センター資料閲覧室 > 固定資産評価研究大会 講演録・討議録 > 第2回固定資産評価研究大会 パネルディスカッション討議録 評価センター資料閲覧室第2回固定資産評価研究大会 パネルディスカッション討議録これからの固定資産税のあり方を考える
 金子 それでは、ただいまから開催させていただきます。これから、固定資産税のあり方を考えるということで、早速パネルディスカッションを始めたいと思います。先ほど、神野先生から「分権型社会における固定資産税について」と題しまして基調講演をいただきましたので、本日はこれに沿って、パネリストの皆様から、ご意見をいただきたいと思います。特に、地方分権の進展に伴って、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充するという視点から住民の受益と負担の対応関係をより明確なものにすると共に、固定資産税が市町村の基幹的な税目として、健全な財政運営を支えていくためには、どのような役割を担っていくべきなのかということについて、諸外国の状況等も併せて、さまざまな立場から固定資産税のあり方を議論していただきたいと思います。 金子 それでは、ただいまから開催させていただきます。これから、固定資産税のあり方を考えるということで、早速パネルディスカッションを始めたいと思います。先ほど、神野先生から「分権型社会における固定資産税について」と題しまして基調講演をいただきましたので、本日はこれに沿って、パネリストの皆様から、ご意見をいただきたいと思います。特に、地方分権の進展に伴って、地方公共団体の財政面における自己決定権と自己責任をより拡充するという視点から住民の受益と負担の対応関係をより明確なものにすると共に、固定資産税が市町村の基幹的な税目として、健全な財政運営を支えていくためには、どのような役割を担っていくべきなのかということについて、諸外国の状況等も併せて、さまざまな立場から固定資産税のあり方を議論していただきたいと思います。このパネルは、全体として4つの問題分野に分けてお願いしたいと思いますが、まず、最初には土地の価格変動が、この10年間の間に激動とも言うべき状況であったということを振り返りまして、議論をしていただきたいと思います。まず、昭和60年ごろ、東京都心の商業地から始まった地価高騰は金融緩和等の環境の中で、3大都市圏、さらには、各地方圏へと波及しましたが、平成2年ごろを境に、地価が反転いたしました。その過程で、地価の変動に対して、固定資産税がどのように対応すべきかが問われたところでございます。そういったことから、これまでの一連の流れを振り返ってみたいと思いますので、各パネラーの皆さんから、それぞれの立場でご発言をお願いしたいと思います。 始めに、地価高騰期において、行政の現場で評価替えについて、いろいろとご苦労され、また体験をしておられます東京都の西村税制部長さんから、お願いいたします。 激動の十年 西村 地価高騰期における土地の評価替えについてでございますが、評価事務という技術的な問題とは別に、いろいろな難しい面がございました。平成3年度までの評価替えにつきましては、今のように評価水準を定める、統一的な基準がございませんでした。適正な時価をいかに求めるかというだけでございました。したがいまして、鑑定価格に対しまして、固定資産税の評価額をどのような割合で決定するかというのは、そのときどきの諸条件を勘案して決めるというのが実態でございました。そういうことで、評価事務にもさまざまな支障を来すことがございました。評価の作業の途中に評価水準を修正するというようなこともございまして、路線価の付設替えをするというような事務に相当の手戻りがあるというようなことがございました。現在では、評価額の上昇率というのは、評価替えの結果として、当然決まっていくわけですが、当時は、各自治体がそうだったと思いますが、3年間の地価の動向と、評価替えに伴う負担増への影響、それを税制改正の動向を見極めながら決めていくということが普通に行われていたと思います。この方式で評価替えいたしますと、評価のアップ率と負担水準は、そのときの状況によって、まちまちにならざるを得なかったということです。全般的には、評価額が低く押さえられまして、納税者の苦情も多くはございませんでしたが、それでも、評価額、あるいは特例額と前年度の課税標準のかい離が大きくなりまして、どうしても負担調整措置というものが必要になりました。そういうことで課税制度が、複雑になるというような問題が生じました。負担調整措置の関係で、地価動向に関係なく、毎年税額が上昇するという問題も残りました。また、公示価格に対する評価の割合が、自治体間はもちろん、自治体の中でも、標準宅地ごとに相違するというようなこともございまして、特に市町村境、あるいは、区境、それから相続税との調整も非常に困難がございました。 金子 どうもありがとうございました。それでは、次に、固定資産税負担のあり方について、外国の税制度に明るい工藤先生から、お話をいただきたいと思います。 工藤 外国の固定資産税負担ということなんですけれども、日本とは若干情勢が違いまして、大体、大陸諸国においては、土地に対する課税というよりは、家屋そのものに対する課税の方が中心だということをご承知おきいただきたいと思います。次に日本との大きな違いとしては、地価の上昇、あるいは、下降と言った変動がそれほど大きくない。それは、そもそも土地の取引が日本ほど激しくないということもありますし、それから、今言ったように、土地そのものに対する課税の重要性がそれほどないために、あまり上下差がないという状況なのです。そのような中で、どういった役割を固定資産税が果しているか、特に税制の中で果しているかと言いますと、最初の基調講演で神野先生もお話されていましたように、地方分権というときに、非常に重要な役割を果たす。つまり、所得税とか、その他の事業税のような変動もありませんし、比較的安定した重要な財源として、固定資産税が主要な役割を果たす。諸外国でも、先ほどの例に出ていましたイギリスでもそうですけれども、その他の国においても、極めて重要で、かつ安定的な財源としての役割を果してきています。そのような中でもしかし、例えば、ロンドンなどだけを例にとりますと、80年代に、極めて投機的な行動がとられてきた結果として、税収上に大きな差をもたらした。特に急速に地価が上がった時点では、やはり負担が相当厳しくなって、ドックランドなど、御存じの方も多いと思いますけれども、企業の方がその負担を負うことができないというような状況が度々起こってきました。それについては、後ほどご説明しようとは思っているんですが、企業と実際に課税をする側の地方自治体とが話し合いをして、ある意味では妥協の結果、その年の税金を決めるというような、かなり柔軟な制度もとられてきています。このようなことは、かなり例外的な措置として、個別事例の積み重ねで行われてきたことなので、あまり制度として発展していたとは言えないのですけれども、急速に地価の上がった時代においては、そのようなことも行われてきています。 あと、先ほど、土地よりも家屋中心ということを申し上げたのですけれども、これは半分笑い話として、あるいは、歴史的なこととして聞き流していただければいいのですが、従来、北ヨーロッパを中心に、コンドミニアム、集合住宅が発展いたしまして、狭い土地に高層の住宅ができる。土地よりも、そういった意味では、住宅、家屋そのものに課税していく方が当然というふうな考え方が出てきたそうです。それに対して、南欧と言いますか、南ヨーロッパ諸国、特に、地中海文明の国では、それほど高層の住宅は発達しなかったのですけれども、一つの連続的な土地に、横向きに集合住宅が出てきまして、かつては、その表面のファサードの門であるとか、窓の立派さから課税をしていたと。それが一番目に見える部分だったので、そこから課税していたという歴史的な背景があるそうです。このことは、何を意味しているかと言いますと、土地よりも、やはり家屋を中心に、家屋の実態であるとか、その利用の方法、それが税金の最も重要なメルクマールになってきたという背景があるかと思います。このことは、基調講演でもやはり、神野先生がお話になっていた土地利用です。土地利用と、特に都市計画との関係の中で税金を決定していくという問題とかかわりがあるのではないかと思います。例えば、イタリアの例で恐縮ですが、今日、イタリアの例を何回かお話する機会があるかと思いますが、私の専門なんですけれども、イタリアの例を出しますと、都市計画の基本というのはそもそも土地利用、特に住宅地をどこにつくるかという、ある意味では、住宅地の線引きと言いますか、区分けをすることが都市計画につながってきたんです。そうしますと、結局、日本で言うと市街化調整区域に当たるようなところでは、どういう戦略的な固定資産税をかけるか、向こうは家屋の税金ですけれども、かけていくかということがかなり重要になってきました。あるいは、郊外型の住宅地を開発していくときには、今後の開発、10年、20年といった長期的な開発に、税金が果たす役割が非常に大きかったということが言えるかと思います。 次に税金の種類ですけれども、これもやはり諸外国共に、一番苦労している点でありまして、目的別にいろいろ税金を課していくというのは非常に合理的そうに見えるのですが、それをやっていくとどういうことが起こるか。今は若干改正されたのですけれども、2年ほど前のイタリアでは、土地とか家屋とか、不動産に何らかの関係を持っている税金が15種類ぐらいという、途轍もない煩雑な仕組みになっていました。これはもちろん納税者にとっても、それから、事務手続きをする自治体の事務としても極めて煩雑なものになってしまって、目的は非常に明らかなんですけれども、このシステムはどうもうまくいかない。ということで、最近では、統廃合して1つにまとめるという簡素化の方向が取られています。恐らく、今後、税金の目的と、それから簡素化ということは、バランスを取りながら、調整していくということになるのかと思いますけれども、諸外国で、最も苦労している点ではないかというふうに思います。 それから、イギリスの例が出ていましたので、最後に1つイギリスのことを付け加えさせていただきますが、御存じの方もあると思いますけれども、ビジネスレイトという、商業活動している建物について、その場所を占有している人が、具体的には、ほとんどこれは賃貸ですので、リースをしている人が、払うお金ということになりますけれども。これ以外には、サッチャーさんが導入して、非常に評判の悪かった人頭税に代わるものとして、新たに加わったカウンシルタックスという居住用の家屋に対して払われるものがありますが、前者の方、つまり、賃貸をしている側が払うという税金は、これは結局、土地、あるいは家屋の面積、評価ということをベースにはしていますが、その商業活動という、そこで行われている生産性ということを加味しておりますので、若干、性格が違う税金が2種類あるということかなと思います。これは珍しいかと言いますと、大陸諸国では、それほど珍しいことではなくて、現在のように、所得が、つまり、収益が悪い企業が不況と共にだんだん増えてきますと、これに課税をすることが非常に難しくなってくる。そのような中で、例えば、活動している、生産活動を営んでいる面積に課税することで、いわゆる、外形標準の考え方を用いることで、比較的安定した税収をもたらすことができるということなんです。そういった意味では、イギリスのみならず、大陸諸国でも極めて常套的に、それぞれの自治体で使われているということを、若干背景は違うかも知れませんけれども、ご紹介させていただきます。 金子 どうもありがとうございました。それでは次に、神野先生から、地価高騰問題の総括、特に金融問題との関連について、お願いしたいと思います。  神野 まず、この10年間を振り返ってみると、日本が世界で1、2の豊かさになったという、10年前にです。そこから歴史が始まったと思うのです。10年前に、私たちは、非常に国際競争力の強い企業をバックにして、1人頭のGNPで、世界第2位という、輝かしい記録をつくって、豊かな国になった。当然のことですけれども、非常に国際競争力が強いわけですから、貿易収支が黒字になると。こういう状態のときに、生活大国、産業大国から生活大国へ、それから、生活者重視へという、政策の転換が叫ばれたのですけれども、これがうまくいかなかったというところに、私は地価高騰の基本的な原因があるのではないかというふうに思います。貿易収支の方は黒字になります。そうしますと、為替の方は変動為替レートですから、当然、円高になります。円高になると、この円高の為替レートというのは貿易可能な財ですね。これだけで決まっちゃいますから、輸出される財、輸出することができる財貨、これの競争力だけで為替が決まるのです。その為替で決まって、他の輸出できない財の価格が評価されてしまう。例えば、電気料金は物すごく相対的に国際的に高くなったと言っても、これは電気は輸出できませんので、こういった財は、為替が高く決まって、円高で決まっちゃいますと、当然高くなるのです。それの一番悲劇を受けるのは、公共サービスでありまして、公共サービスは当然ですけれども、突然、円高になってしまうと高くなってしまう。そうすると、日本の政府は国際的に見て非常に非効率的なんだと。だから行革をしなさいという、こういう圧力が加わってくる。同時に、土地もそうでして、土地も当然、輸出できませんから、円高で評価されると、突然ある日、アメリカの何倍の価格に日本の国土がなっちゃったというようなことが起きてきた。このときに、貿易収支の大幅な黒字を弱めるために、むしろ財政を膨脹させて、特に地方財政を膨脹させて、生活大国、あるいは、生活者重視の国のための政策にお金を使っておけばよかったのですが、そうはしなかった。当然、円高になって不況になる。円高不況に陥ったときに、財政を膨脹させ、先ほど言いました地方財政を膨脹させずに、円高になったために不況になったから、これを金融政策で行おうとしたわけです。打たれたのが低金利政策で金利を非常に低めて、そして、企業の設備投資を高めて、そして、輸出競争力を高めようと、こういうふうにしようとしたわけですけれども、企業の方は、もう設備投資をするような需要はなかったものですので、ストック、常にあるものを買うという方向に動いたわけです。ストックの中で最も安定しているものは何かと言いますと、それは土地であって、土地と株が投機の対象になって、御存じのとおり、絵も対象になりましたけれども、低金利政策によって、ちまたに溢れ出たお金がすべて土地とか株式に向かっていった。土地の方、ただでさえ円高でもって高くなっているところが、どんどん低金利で溢れたお金で買いあさられましたので、御存じのバブル景気ができあがった。今度はそのバブル景気はいずれ崩壊するわけです。なぜなら、新しくフローとして、できてくるものに見合ったお金が出てきてるわけではなくて、既につくられてあるものだけが、言わば花見酒の経済のように売り買いをされて、どんどん値が上がっていくことによって、価格が上がっていくわけですから、いずれ、そのバブルは弾ける。弾けたら、今度は、逆回転いたします。全く効果が逆の方に動き始めまして、特に重要なのは、一方で生活大国を目指したようなきちっとしたセイフティーネット、安全ネットを張るような政策を打っておかなかったものですから、人々は不安に怯えますので、どんどん消費を控えて、貯蓄に回すようになる。消費需要はどんどん減っていく。需要がないものですから、価格はどんどん下がっていってデフレスパイラルになる。そのときに、一番悲劇を被るのは、土地でありまして、この土地の価格がどんどんひきらはっていく。 神野 まず、この10年間を振り返ってみると、日本が世界で1、2の豊かさになったという、10年前にです。そこから歴史が始まったと思うのです。10年前に、私たちは、非常に国際競争力の強い企業をバックにして、1人頭のGNPで、世界第2位という、輝かしい記録をつくって、豊かな国になった。当然のことですけれども、非常に国際競争力が強いわけですから、貿易収支が黒字になると。こういう状態のときに、生活大国、産業大国から生活大国へ、それから、生活者重視へという、政策の転換が叫ばれたのですけれども、これがうまくいかなかったというところに、私は地価高騰の基本的な原因があるのではないかというふうに思います。貿易収支の方は黒字になります。そうしますと、為替の方は変動為替レートですから、当然、円高になります。円高になると、この円高の為替レートというのは貿易可能な財ですね。これだけで決まっちゃいますから、輸出される財、輸出することができる財貨、これの競争力だけで為替が決まるのです。その為替で決まって、他の輸出できない財の価格が評価されてしまう。例えば、電気料金は物すごく相対的に国際的に高くなったと言っても、これは電気は輸出できませんので、こういった財は、為替が高く決まって、円高で決まっちゃいますと、当然高くなるのです。それの一番悲劇を受けるのは、公共サービスでありまして、公共サービスは当然ですけれども、突然、円高になってしまうと高くなってしまう。そうすると、日本の政府は国際的に見て非常に非効率的なんだと。だから行革をしなさいという、こういう圧力が加わってくる。同時に、土地もそうでして、土地も当然、輸出できませんから、円高で評価されると、突然ある日、アメリカの何倍の価格に日本の国土がなっちゃったというようなことが起きてきた。このときに、貿易収支の大幅な黒字を弱めるために、むしろ財政を膨脹させて、特に地方財政を膨脹させて、生活大国、あるいは、生活者重視の国のための政策にお金を使っておけばよかったのですが、そうはしなかった。当然、円高になって不況になる。円高不況に陥ったときに、財政を膨脹させ、先ほど言いました地方財政を膨脹させずに、円高になったために不況になったから、これを金融政策で行おうとしたわけです。打たれたのが低金利政策で金利を非常に低めて、そして、企業の設備投資を高めて、そして、輸出競争力を高めようと、こういうふうにしようとしたわけですけれども、企業の方は、もう設備投資をするような需要はなかったものですので、ストック、常にあるものを買うという方向に動いたわけです。ストックの中で最も安定しているものは何かと言いますと、それは土地であって、土地と株が投機の対象になって、御存じのとおり、絵も対象になりましたけれども、低金利政策によって、ちまたに溢れ出たお金がすべて土地とか株式に向かっていった。土地の方、ただでさえ円高でもって高くなっているところが、どんどん低金利で溢れたお金で買いあさられましたので、御存じのバブル景気ができあがった。今度はそのバブル景気はいずれ崩壊するわけです。なぜなら、新しくフローとして、できてくるものに見合ったお金が出てきてるわけではなくて、既につくられてあるものだけが、言わば花見酒の経済のように売り買いをされて、どんどん値が上がっていくことによって、価格が上がっていくわけですから、いずれ、そのバブルは弾ける。弾けたら、今度は、逆回転いたします。全く効果が逆の方に動き始めまして、特に重要なのは、一方で生活大国を目指したようなきちっとしたセイフティーネット、安全ネットを張るような政策を打っておかなかったものですから、人々は不安に怯えますので、どんどん消費を控えて、貯蓄に回すようになる。消費需要はどんどん減っていく。需要がないものですから、価格はどんどん下がっていってデフレスパイラルになる。そのときに、一番悲劇を被るのは、土地でありまして、この土地の価格がどんどんひきらはっていく。今、こう見ていきますと、この10年間、私たちは、結局、生活立国、生活大国に根ざすような政策の転換というのが、計画はできたのですけれども、計画倒れに終わってしまった。そのために、土地という人々の生活の最も軸になっていかなければならないようなものが、金融の低金利政策のために投機の対象となって、価格の乱高下にあえいでしまったというのが、土地を巡る価格の乱高下の実態だったのではないか。先ほども言いましたように、こうしたデフレスパイラルを切り取るには、もう一度、生活大国になるための政策を打ち直すということが必要なのではないか。そのことによって、土地の価格は安定し、人々の生活というものが安定されるのではないかというふうに考えています。 金子 どうもありがとうございました。それでは、続きまして、行政の立場から、固定資産税における制度的対応はどうであったのか、また、どう取り組まれてきたのか、こういう点について、これまでの状況について、自治省の武田課長さんから、お願いいたします。どうぞ。 武田 それでは、この激動の10年間、固定資産税制度がどう変化してきたかというあたりを少しふりかえってみたいと思います。特に変化があったのは土地ということになろうかと思いますが、いわゆるバブル期に大都市部を中心に大幅な地価高騰がございました。そのときに、議論がいろいろありましたが、1つは、この地価高騰の要因と言いますか、それをどう分析するかということで、例えば、先ほど、西村部長からもお話がありましたが、実際の地価と固定資産税の評価額とに大きなかい離が生じている、固定資産税の評価の方が低いというわけですが、そのことが土地を結果的に有利な資産にしてしまう、それで地価上昇に結びつくんだ、こういうふうな言い方をされておりました。主たる原因としては、今、神野教授が言われましたように、金融問題が大きな要因だろうというふうに思うわけですが、税制上も何らかの対応をする必要があるのではないかという議論になりました。しかし、そのときに、固定資産税をいわば政策税制として、大きく変化をさせるというのはいかがなものだろうかということで、あくまで、固定資産税というのは、市町村の基幹的な税目でありまして、そういうことで、いわば、政策目的、地価を抑制をする、あるいは、短期転売を防止する、あるいは、有効利用を促進する、こういうふうな政策目的のためには、地価税でありますとか、譲渡課税、あるいは、特別土地保有税、こういったものを活用するというふうな対応がとられたわけです。 一方、もう1つ、別の議論として、固定資産税を含む公的な土地評価についての議論がございました。先ほどの神野先生の基調講演にもありましたが、いわゆる、一物四価というのがよく言われたわけです。そういった公的土地評価がばらばらでいいのだろうか。特に、地域や土地によって、大きくその度合いも異なっている。そういうような状況の中で、土地基本法という、土地施策の憲法とも言うべき、法律ができたわけでありますが、その土地基本法の16条に公的土地評価についての相互の均衡・適正化を図るべきだという規定が盛り込まれたわけです。これを受けまして、閣議決定である総合土地政策推進要綱、あるいは、中央固定資産評価審議会、また、税制調査会、こういったところで種々の検討がなされた結果、平成4年から相続税評価が地価公示の8割水準を目途に行われることになり、固定資産税については、平成6年度の評価替えから地価公示の7割を目途に評価をするということで、それぞれ公的な土地評価の関連が明確になったということが1つ大きな変化でありました。その結果、平成6年度の評価替えが、これまでとは全く様子の違う評価替えになったわけです。ご案内のように、全国平均で3.96倍という評価上昇を見たところです。こういった評価の上昇に対応して、平成6年度、7年度、8年度ということで、税負担の急増を避ける必要があるという観点から、負担調整措置を講じたわけです。前年度の課税標準額を少しずつ伸ばすという形で、税負担の急増を防止をしたわけです。平成9年度の評価替えのときには、地価がまだ下がっているということで、全国平均で25%の評価見込の下落がありました。しかし、内容を見ますと、大都市部では40%落ち、都市部では15%、町村部では5%ということで、地域によってかなり、その地価下落の状況も異なっておりました。変動にも相当のバラツキが出てきているということで、各土地における負担水準の不均衡というものが次の大きな問題になってきたわけです。言うならば、平成6年度のときに、評価の水準は、同じ全国一律の物差しで統一をされたということになったわけですが、しかし、一方で同じ評価に対する課税標準の割合、いわゆる、税負担水準の不均衡というものが非常に大きな課題となってきたわけです。そこで、この税負担水準をいかにして均衡化をさせるかということで、平成9年度には、これまでにない新しい負担調整の仕組みをとり入れることにいたしました。最終的には、新しい評価額に100%追いつくというのが、従前の負担調整の考え方であります。平成9年度は、いわゆる評価の100%を目指すということではなしに、負担水準をできるだけ均衡化させるということから、負担水準が80%を超えているような土地については、80%になるまで課税標準を引下げましょうということにいたしました。それから、60%から80%の間にある土地については据え置きにします。60%未満の負担水準の土地は、少しずつ引上げをしていきましょうということで、いわば、100%に向かって、みんなが少しずつ上がっていくのではなしに、高いものは下げ、低いものは上げていく。そういう中でできるだけ全国的に土地の負担水準、即ち、評価に対する課税標準の割合を近づけていこう、こういう取り組みをしたところです。 また、一方で地価下落がまだ続いている地域もあるということで、平成10、11という、いわゆる据え置き年度におきましても、下落修正をすることができるという措置を講じまして、平成10年度では、全国で1,739団体、53.8%の団体で下落修正に取り組んだところであります。その結果、評価見込は約3.4%の減というふうになる見込です。平成12年度以降、さらに、この負担の均衡化、適正化を図るというのが、一番の土地を巡る固定資産税の課題であるということで、これに向けて、どのような仕組みにしていくのが適正、公平な課税にするために必要かという観点から、今、種々の検討を行っている、そういう状況であります。  固定資産税における納税者の役割 金子 どうもありがとうございました。地価の変動に対して、各方面からのさまざまな対応について振り返っていただきましたが、次に、第2番目の問題点として「固定資産税における納税者の役割」という問題に移っていきたいと思います。固定資産税がより一層簡素かつ合理的な制度を目指し、そして、納税者へのさらなる理解を求めるためには、その課税システムの過程で、住民との共同作業が不可欠となってくるわけでございます。そこで、固定資産税における申告や、不服の申し立て等のあり方を探ってみたいと思います。申告納税制度の意義と賦課課税制度の意義などにつきまして、神野先生から、まず、お願いいたします。 神野 まず、私は財政を専門にしておりますので、経済学部の方の財政ですので、税務行政上の知識はあまりないのですが、そのために、やや素人談義に終わってしまうかも知れませんが、基本的には、私は税額を納めると言いますか、税額を納めるための申告納税と、賦課課税ということを考えると、こういう固定資産税のような税金は、基本的には税額について言えばですが、賦課課税をとらざるを得ないのではないかというふうに考えています。ただ、税金というのは、ご存じのとおり、課税客体、どういう事実、あるいは、どういう物件に税金をかけるという課税客体が決まり、その課税客体を数量化した課税標準が決まり、そして、その課税標準に税率をかけて税額が決まるわけです。その税額については、恐らく、賦課課税方式が基本にならざるを得ないとは思いますけれども、今、金子先生がお話になりました納税者の役割というような納税者の参加、協力作業というような意味から言うと、課税客体に関して言うと、ここについて、申告と申しますか、納税者の協力というようなことがあり得るのではないか。したがって、課税客体ないしは、課税標準、こういう問題について、納税者協力というのでしょうか。それを申告方式として、取り入れられる余地というものがあり、それを拡充させていく必要があるのではないかというふうに考えます。 アダム・スミスの税金の原則から言うと、公平性と、それから、税務行政上の原則があって、税務行政上の原則の中に便宜と明瞭性と、それから、徴税費最小の原則がありますけれども、そのうちの明瞭性にかかわることとして申告を生かしていくことによって、納税者の理解を深めていくということがあり得るのではないかというふうに考えています。それと同時に、したがって、課税客体について、納税者の協力、申告というような制度を利用すると同時に、そういう税務行政上の明瞭性という観点から言うと、恐らく、課税客体についての申告と言っても、最終的な税額について賦課課税方式をとる以上、その申告というのは、納税者にとってメリットになるようなことを軸にして、申告制度を活用していかなければならないだろうと思うのです。そうすると、そのメリットに対するチェックが必要になってくるわけで、そのチェックは、これはシャウプ勧告も言っていますが、固定資産税内部で、完結するような課税客体の明瞭性ではなくて、他の税目、他の、例えば、財産課税とか、あるいは、法人税の減価償却とか、他の税目とのチェックアンドバランスによって、納税者の申告をチェックするというようなシステムをつくり上げてメリットの申告性を導入していくという方向を検討すべきではないかというふうに考えています。 金子 どうもありがとうございました。続いて、西村部長さんには、申告や審査申出、不服の現状と問題点につきまして、実務的にどうであったかの分析を含めて、お話をお願いいたします。 西村 始めに、審査申出関係のことについて、納税者の協力ということで、お話を申し上げたいと思います。先ほど、武田課長さんから、平成6年度以降の評価替えの話がございました。地価公示価格の7割を目標に、全国的に統一した評価水準が確保することができたということで、全国の市町村間、それから、相続税との関係でも、基本的には評価の均衡が図られたということで、これは画期的なことであったと思います。まず、各自治体の政策的な判断の余地が入らないということで、評価事務も飛躍的に円滑に進めることができるようになったと思います。これは固定資産税制度にとりまして、大変大きな前進であったというふうに思います。しかしながら、地価が下落する中で、評価額が6年度には大幅に上昇いたしました。その後も、地価が下落する中で、税負担が上昇するという状況もございました。この評価替えによりまして、納税者には大きな負担感を与えてしまったということも事実でございます。大都市の負担水準の高さと、税額の相対的な大きさなど、納税者から出された問題が顕在化する一面もございました。また、さまざまな負担調整措置を講じたために、税額算定の仕組みが一段と複雑化した面もございました。大量の審査申出が出され、納税者対応に大変苦労したわけでございますが、東京都におきましては、平成6年度の審査申出が2,300人を超えまして、審査委員を9名から15名に増やすと同時に、その事務局についても、充実を図ったところですが、全部の審査申出を処理するのに3年を要しました。そのために、9年度の評価替えに当たりましては、この評価に対する不服申し立ての迅速な解決手段として、再調査というものを東京都独自の方法で積極的に活用することにいたしました。その再調査の方法につきましては、不服や苦情がありましたときに、納税者と共に、現地で再調査をする。納税者のご意見を聞くというような形で、9年度におきましては、土地家屋併せまして1,400件を越す再調査を行ないました。それに対しまして、審査申出の方は870件余ということで、相当の効果があったというふうに思っております。この再調査は、窓口で苦情があったときに、即日、処理をするということを建前にして取り組んできました。そして、即日処理を含めまして、1,400件余は、全件につきまして、30日以内に結論を出し、修正すべきものは修正をして、正しい内容で納税通知書をお送りしたということでございます。この再調査につきましては、実際のやり方は多少異なるかも知れませんが、他の団体でも行っているというふうに聞いておりますが、これを制度化する価値があるのではないかと思っております。そういうことで、審査申出の処理を迅速化する方法の一つとして、この再調査が非常に効果があったと思います。今後、固定資産税の評価にも何らかの形で、納税者が加わることが避けられないのではないかというふうに考えております。そこで、その参加の方法について、具体的にかつ積極的に検討していくことが望ましいのではないかというふうに思います。その他、納税者の協力を得て、固定資産税の課税事務、評価事務を進めているものがございます。非課税、あるいは、減免に関します申告、あるいは、申請が一般的に行われておりまして、それはそれなりに役割を果していると思います。住宅用地につきまして、特例制度が設けられましたときに、やはり申告制度も同時に導入されました。しかしながら、その活用については、各自治体によって差があるのではないかというふうに思います。東京都におきましても、なかなか申告が得られないということから、不公平な取り扱いがあるということがございまして、平成6年から3年間かけまして、実地に調査をしましたが、大変な手数がかかりました。したがいまして、この制度につきましても、十分機能するように、見直し、充実を図っていく必要があるのではないかと思います。評価の面で広く申告制度を利用しておりますのが、ご案内のとおり、償却資産の申告でございますが、これは償却資産の課税客体の最も基本的な捕捉の方法として行っておりますけれども、不申告、あるいは、申告漏れというものが少なくなく適正公平な課税を確保するという点では、具体的な調査によりまして、適正化措置を十分にやりませんと、申告制度そのものを損ねるという危険があるというふうに考えています。これにつきましても、2、3年来、法人、あるいは、個人企業の事業所に行きまして、帳簿調査等をやり、その申告制度の不十分な点を実地調査で補っているというのが現状でございます。また、土地家屋の評価につきましても、申告の活用ができないかということですが、外国では、評価資料とするために、納税者が当該資産の取得価格の申告等を行っているやに聞いております。制度、それから、習慣の異なる日本での実現は、困難が大きいと思いますが、研究をしていく価値はあるんではないかというふうに思います。昨年、この資産評価システム研究センターで行ったアンケート調査の結果では、例えば、家屋評価に取得価格方式を導入するということに賛成と言いますか、望むというのは13%に過ぎなかったと言われますが、13%もあったのかというふうにも考えられます。家屋につきましては、特に評価事務の負担が大きいというふうに思います。また、納税者にとりましても、家屋評価の仕組みが専門的で非常にわかりにくいということで、行政側でした評価に対する不満も多くなる傾向がございますので、何とか納税者の協力を得ながら、評価事務の簡素化を図り、わかりやすいものにしながら、適正な評価額を把握するという方法を今後検討していくといいのではないかというふうに考えているところでございます。 金子 どうもありがとうございました。こうした申告や、不服に対して、諸外国では、どのようになっているのかということを、ヨーロッパの資産税について研究をしておられます工藤先生に、イタリアやイギリスの例などについて、ご紹介いただければと思います。  工藤 今の西村さんのお話の中でも出ていたように、申告における納税者の役割ということについては、外国の例は確かに違いますので、そのへんのお話をしたいと思います。まず、例えば、イタリアなどでは、申告に関しましては、家屋の取引の実態から始まって、実際の税額の算出も自分で行うような書式がついておりますので、そのインフラストラクションに従って書込みをしていく。この発想は、それぞれの納税者によって、減税のさまざまな措置などが違いますので、と言いますのは、具体的には、例えば、年金生活者が1人で住んでいる場合、あるいは、年金生活者のカップルが住んでいる場合、あるいは、他に住宅がなくて、その家を主たる自分の生活の場、自宅としている場合、あるいは、それが別荘地である場合など、すべて違いますので、それは本人にしかわからないというのが原則になっております。 工藤 今の西村さんのお話の中でも出ていたように、申告における納税者の役割ということについては、外国の例は確かに違いますので、そのへんのお話をしたいと思います。まず、例えば、イタリアなどでは、申告に関しましては、家屋の取引の実態から始まって、実際の税額の算出も自分で行うような書式がついておりますので、そのインフラストラクションに従って書込みをしていく。この発想は、それぞれの納税者によって、減税のさまざまな措置などが違いますので、と言いますのは、具体的には、例えば、年金生活者が1人で住んでいる場合、あるいは、年金生活者のカップルが住んでいる場合、あるいは、他に住宅がなくて、その家を主たる自分の生活の場、自宅としている場合、あるいは、それが別荘地である場合など、すべて違いますので、それは本人にしかわからないというのが原則になっております。それから、これは固定資産税だけではなくて、他の税金についても同じことが言えるのですが、基本的に、その場合には、性善説に立っていると。財政学者も言っております。ただ、これだけでは、当然、脱税とか、また脱税しようという意図はなくても、ミス等も沢山起こりますので、これもきわめてヨーロッパ的な発想ですけれども、大陸諸国で典型的なペナルティー制度をとっています。恐らく、例えば、諸外国、特に大陸諸国に行かれて、市電などにお乗りの方は、最初戸惑われると思いますが、車掌さんもいなければ、日本のワンマンバスのように、お金を払うところもない。どうやら土地の人を見ていると、チケットをおもむろに機械に差し込んで、日時をスタンプしている。やっていない人もいる。何なのかと言いますと、大体タバコ屋さんのようなところでチケットを先に買いまして、自分で乗るときには、それにスタンプを押して使う。全くコントロールがないわけです。これは皆さん最初に行かれると、非常に驚くわけですが、文化的に、子供時代からずっとそういう経験をしておりますと、基本的にそれは義務として、自分はやる。中には、確かに逃れようとか、払い忘れてしまうという人もいますが、これには実は、ときどきコントロールをする検札が回ってきまして、一端捕まると、通常料金の大体20から40倍という高額の罰金を取られるというのが、社会の仕組みとして定着しています。ですから、そのへんは、若干日本の公共意識とは違うかも知れませんけれども、税金についても同じことが言えまして、例えば、万一ミスが発覚したというような場合には、これは実際に脱税の意図があったかないかにはかかわらず、ペナルティーが科されるということになってます。抜取り調査は必ず行っておりますので。特に商業活動の激しい地区、具体的に今のイタリアの例で申しますと、ミラノであるとか、ローマであるとか、大都市に関しては、相当数の抜取り調査をして、調べるといったようなことが行われています。一部のジャーナリストに言わせると、実は、9割ぐらいは何らかの間違いがあるんだということですが、それについては、当然、追徴が行われてきております。また、そこにもう一つある考え方として、税金というのはそもそも、義務として国民がやらなければいけないことの一つというよりは、実際に自分たちが受けているサービスの対価を払うのであるから当然である、という行政側の基本的な考え方があるかと思います。 その中で、そのいかに脱税や、ミスを減らして、意図的に少なく申告をする人を減らすかという工夫も行われています。それは、なるべく多くの人から、万遍なく、平等感を持った状態で、普遍的に税金を取ろうということです。これは実際には、例えば、イタリアでは固定資産税に当たる市の不動産税というものがありますけれども、これを全国平均で均していくと、大体、実際の年間の税額というのは2万円ちょっとぐらい、日本円にしますと2万円少々になっております。先ほども例に挙げたイギリスですけれども、イギリスの方が若干高いですが、それでも、例えば、さまざまな控除がありますので、年金生活者のカップルであれば、それこそ2万円以下の税金を払えばいいというように、日本的な感覚から言えばかなり低い水準になっていますけれども、これでも一部からは高いと考えられていまして。より平等に広くとることで、申告者がうそをついたり、意図的に低く申告しようということを避けようという動きがあります。ただ、そうは言いましても、この申告そのものを全部納税者側に委ねるということには、裏の保障もありまして、それは不服申し立てのシステムです。イタリアについても、不服申し立てはかなり行われているんですけれども、皆さんにご紹介するものとしては、イギリスが面白いのではないかと思うので紹介させていただきます。 レイトという土地建物家屋の評価を決める決め方なんですけれども、これは5年に1回評価替えが行われますが、そのときには、国から任命された、実際には市町村のレベルで組織された、レイトを決める、評価を決める人たち、専門官が調査にまいります。必ずと言っても、正確には抜取りなんですけれども、調査にまいりまして、そこの家屋の評価を決めます。これに実は、不服申し立ての機関というのがありまして、そのときに、もしも、それが不当に高いであるとか、あるいは、前回とは違った利用をしているために、評価の表がありますのが、その中で自分は違ったところに属するようになるなど状況が変わったとか、あるいは、何らかの不服がある場合には、最初は実際の、その調査官との妥協の道を探ります。ここで、自分たちは、例えば周囲の家屋の評価と比べて自分のところは不当に高いとか、あるいは、何か状況が違ったという証拠を持って、必ず代替案を提示しなければいけないと言われてます、その代替案と、評価委員会の方とですり合わせをして、合意に達しますと、めでたくその合意の価格が評価価格として決まっていくという、かなり参加型と言うか、実際に利用者が評価そのものにかかわれるという面白い仕組みになってます。もしも、両者間において、合意が成立しなかった場合、その地域ごとに設けられるバリュエーショントリビューン、評価の裁判所といった、実は、裁判所と言いましても、弁護士さんがいたり裁判官がいるというよりは、委員会形式のものなんですが、そこに持ち込まれます。ケースがそこに持ち込まれても、実際に話し合いの場に持ち込まれる前に解決するという場合も沢山あるそうで。最終的には、そこの審査で決まった価格が評価価格として採用されるということになっております。さらに、それでも、やはり自分は納得いかないという場合には、最終的に司法的な手続きが残されていまして、1か月程度以内に、全国レベルで行われているランドトリビューン、土地裁判所というふうに通常訳されているかと思いますが、そこに持ち込む。そこでは、当然、司法的な解決に入るということになるわけです。ところが、これにも非常に緩やかな救済策が沢山用意されておりまして、30日間と言っても、後で考えてみると、よくよく考えると、どうもこの評価は納得いかないという人もおりますので、この30日という条件は、実際はかなり緩やかに運用されているのが実態だそうです。ですから、イタリア、イギリス共に、申告の面でも、納税者側が相当参加をする。いい言葉で言えば参加で、ちょっと厳しい言い方をすれば、その義務が増えるということかもしれませんけれども。それには、不服申し立ての面でも、つまり、評価を考えるところにも参加できるという保障があってできているということが言えます。 ちなみに、こんなに沢山の業務をするイギリスは、さぞかし不動産関係の職員が多くて大変なのではないか、というふうに、自治体の方で思われている方も多いかと思いますが、実際は、例えばトリビューンという委員会ですけれども、この審議会は必ずしも、全員が市の職員、あるいは、その専門家ではないのです。もちろん、不動産の知識のある民間の業者の方ですとか、いろいろな方、場合によっては、この紛争解決の調停員のようなものの経験のある主婦の人とか、地元の人が入って、構成されています。ですから、これはむしろ調停の場ということを提供しているわけで、最終的に、その司法解決のランドトリビューンという方に行くそうです。ですから、実は、それほど、職員の数は多くないそうであります。もちろんイギリスは、非常に不動産市場、あるいは不動産鑑定に関して盛んな国ですので、不動産学部というような大学の学部も沢山ありますし、不動産関係者というのは多いのですが、必ずしも、職員の数はそれほどではない。それでも、十分できるのだそうです。ということを付け加えたいと思います。私からは、以上です。 金子 どうもありがとうございました。固定資産税における納税者の役割の問題は、制度をどうするかの問題でありますので、現行制度はどのようになっているのか、また、種々の問題点について、今後いろいろと手を加えなければならないと思いますが、どのよに考えるのか、その検討状況等につきまして、武田課長さんから、お願いいたします。  武田 固定資産税というのはご案内のように、賦課課税方式をとっているわけです。申告納税方式ではなくて、賦課課税方式ということで、基本的には、課税庁であります市町村が調査をし、確定をし、徴収をするという手続きをとっております。しかし、その現行制度の中でも、一部納税者の参加をいただきながらやっている、納税者の役割も期待をしている部分も一部ありまして、その中から、1つは、いわゆる、審査申出の話、もう1つは申告制度の手続きということで、少し、お話をしたいと思いますが、ご案内のように、審査申出、これは固定資産課税台帳の縦覧の期間が始まりましてから、その末日後10日までという期間内に、その審査申出をすることができるということです。これも先ほど、お話しましたように、平成6年度の評価替えで、7割評価ということで、評価額がかなりアップをしたということも影響したんだと思いますが、平成6年度の評価替えの際に、審査申出が増えました。全国で2万2,000件余の審査申出がございました。平成9年度は、若干減りましたけれども、それでもまだ、1万3,000件余の審査申出がございました。この中で、平6から平9にかけて土地に関しての審査申出は、約半分に減ったのですけれども、家屋の方は、逆に、倍に増えるというようなことで、納税者の関心の方も、少し変化が見られるのかなという気もいたしますが、いずれにしても平6、あるいは平9におきまして、この審査申出、非常に膨大な数に上っております。現在の地方税法の仕組みでは、この審査申出を受けた固定資産評価審査委員会におきましては、30日以内に、審査の決定をするということが規定をされておりますが、実際には、これだけの多量の申出が出てくるというようなこともあり、30日以内に決定できた件数というのは、数%からせいぜい1割程度というような団体がほとんどであろうかと思います。そういうことで、私ども、今後の検討課題としては、この評価審査委員会における審査の迅速化ということが大きな課題ではないかと思っております。委員会の運営をできるだけ円滑に進めるということで、資料請求のあり方であるとか、あるいは、審査申出事項の合理化、また、現在原則として、口頭審理によっております審理手続きのあり方等を中心にして、審査の迅速化に向けての見直しを進めたいと考えております。不服申し立てに対する結論をできるだけ早く出すということは、納税者にとっても決して不利なことではないと思います。結論が出て、さらに、それに不服があるという場合には、訴訟を提起するという道もございますので、こういった行政部内における審査申し立て制度というものは、やはりできるだけ早く結論を出していくということが必要ではないかと思います。それから、一方、審査申出、先ほど申し上げましたように、縦覧期間の末日後10日までという期間制限をいたしております。しかし、実際、各市町村からいろいろ話を聞きますと、納税通知書が届いてから、それを見て不服を申し立てたい。これはどうも納得できないというふうに窓口に駆け込んでこられる方が結構多いというお話をお伺いします。この状況に対しましては、考え方は2つあろうかと思いますが、納税者サイドで、一方で縦覧をする、そういうチャンスがあったんだから、縦覧をしないで、その後、納通が届いてから不服を言われても、それは仕方ないじゃないでしょうかという考え方が1つ。もう1つは、実態的に、大勢の方が、そういう不服を持っておられるのであれば、納税通知書到達後であっても申出ができるような、そういうふうに実態を踏まえて、見直しをしたらいいのではないか。こういう意見もございます。ここらへんは、納税者の現在の状況も十分踏まえながら、固定資産税として、納税者により理解されるためにはどうあるべきかということで検討をしていきたいと思っております。 武田 固定資産税というのはご案内のように、賦課課税方式をとっているわけです。申告納税方式ではなくて、賦課課税方式ということで、基本的には、課税庁であります市町村が調査をし、確定をし、徴収をするという手続きをとっております。しかし、その現行制度の中でも、一部納税者の参加をいただきながらやっている、納税者の役割も期待をしている部分も一部ありまして、その中から、1つは、いわゆる、審査申出の話、もう1つは申告制度の手続きということで、少し、お話をしたいと思いますが、ご案内のように、審査申出、これは固定資産課税台帳の縦覧の期間が始まりましてから、その末日後10日までという期間内に、その審査申出をすることができるということです。これも先ほど、お話しましたように、平成6年度の評価替えで、7割評価ということで、評価額がかなりアップをしたということも影響したんだと思いますが、平成6年度の評価替えの際に、審査申出が増えました。全国で2万2,000件余の審査申出がございました。平成9年度は、若干減りましたけれども、それでもまだ、1万3,000件余の審査申出がございました。この中で、平6から平9にかけて土地に関しての審査申出は、約半分に減ったのですけれども、家屋の方は、逆に、倍に増えるというようなことで、納税者の関心の方も、少し変化が見られるのかなという気もいたしますが、いずれにしても平6、あるいは平9におきまして、この審査申出、非常に膨大な数に上っております。現在の地方税法の仕組みでは、この審査申出を受けた固定資産評価審査委員会におきましては、30日以内に、審査の決定をするということが規定をされておりますが、実際には、これだけの多量の申出が出てくるというようなこともあり、30日以内に決定できた件数というのは、数%からせいぜい1割程度というような団体がほとんどであろうかと思います。そういうことで、私ども、今後の検討課題としては、この評価審査委員会における審査の迅速化ということが大きな課題ではないかと思っております。委員会の運営をできるだけ円滑に進めるということで、資料請求のあり方であるとか、あるいは、審査申出事項の合理化、また、現在原則として、口頭審理によっております審理手続きのあり方等を中心にして、審査の迅速化に向けての見直しを進めたいと考えております。不服申し立てに対する結論をできるだけ早く出すということは、納税者にとっても決して不利なことではないと思います。結論が出て、さらに、それに不服があるという場合には、訴訟を提起するという道もございますので、こういった行政部内における審査申し立て制度というものは、やはりできるだけ早く結論を出していくということが必要ではないかと思います。それから、一方、審査申出、先ほど申し上げましたように、縦覧期間の末日後10日までという期間制限をいたしております。しかし、実際、各市町村からいろいろ話を聞きますと、納税通知書が届いてから、それを見て不服を申し立てたい。これはどうも納得できないというふうに窓口に駆け込んでこられる方が結構多いというお話をお伺いします。この状況に対しましては、考え方は2つあろうかと思いますが、納税者サイドで、一方で縦覧をする、そういうチャンスがあったんだから、縦覧をしないで、その後、納通が届いてから不服を言われても、それは仕方ないじゃないでしょうかという考え方が1つ。もう1つは、実態的に、大勢の方が、そういう不服を持っておられるのであれば、納税通知書到達後であっても申出ができるような、そういうふうに実態を踏まえて、見直しをしたらいいのではないか。こういう意見もございます。ここらへんは、納税者の現在の状況も十分踏まえながら、固定資産税として、納税者により理解されるためにはどうあるべきかということで検討をしていきたいと思っております。それから、申告ですが、固定資産税はもとより、本来的な申告納税方式をとっておりませんので、いわば、現在の賦課課税方式を補完する一部の手続きとして採用をしているものでございます。現在、383条にもとづく償却資産の所有者からの申告、それから、384条にもとづく住宅用地の所有者からの申告、それぞれ課税対象の把握でありますとか、特例の適用にとって必要だというような観点から、申告をお願いをしているところですが、先ほど、神野先生からもございましたように、納税者にとっても、また課税庁にとっても、チェックアンドバランスという観点から、納税者に主体的な協力をさらにお願いをしていくということも必要なのではないかなと思っております。何でもかんでも申告というわけにはまいらないと思いますけれども、納税者のそういった申告が公平適正な課税にとって有意義な場合というのもあろうかと思いますので、そういった観点から納税者の申告制度も活用するようなことを、これから検討をしていきたいと思っているところです。 地方分権と固定資産税 金子 どうもありがとうございました。それでは、次に、第3番目の問題点として、地方分権と固定資産税の問題に入っていきたいと思います。先ほど、神野先生の基調講演でお話がございましたように、地方分権の伸展と共に、地方公共団体では、ハードの社会資本中心の公共サービスから、福祉医療などの対人社会サービスが増加することになり、その増加するサービスに対して、必要財源を賄っていかなければならないということになるわけであります。住民の施策選択の手段としての役割が期待されるという観点から、基幹税としての固定資産税のあり方について、ご意見をいただきたいと思います。そこで、まず、地方分権推進委員会の専門委員の座長でもある神野先生から、地方分権の動きと地方税制のあり方について、お願いいたします。 神野 長くなるといけませんので、簡略に申し上げますと、ご案内のとおり、地方分権推進委員会の勧告の第二次勧告、そして、それに基づいて、5月29日でしたか閣議決定されました地方分権推進計画でも、地方の歳出と、それから国の歳出との格差が国税と地方税の格差とあまりにも乖離しているので、それを是正する方向で将来とも地方税を充実させていくというのが基本方針でございます。そして、その中で第二次勧告でもうたってございますが、今後、生活者重視と勧告の中で書いておりますけれども、今、お話のように、福祉サービスみたいなもの、対人社会サービスですね。こういったものが中心に移っていきますので、そういった財源というのは、これまでのような固定資産税だけに異存するというような、これは固定資産税だけではありませんけれども、固定資産税を中心として、地方税を描くというような、特にイギリスやアメリカで行われていたような方式が少し無理で、少なくとも、対人社会サービスに対応した地方消費税とか、住民税も増やしていくというのが、恐らく、趣旨だろうと思います。ただ、かと言って、固定資産税が、ウェートが重要性がなくなるのかということではなくて、固定資産税も繰り返すようですけれども、対人社会サービスと無関係ではない。先ほど言いましたように、個々のサービスと対応しているわけではなくて、全体のサービスに対する利益を出しますので、そういった観点から、固定資産税も先ほど工藤先生がおっしゃいましたけれども、普遍的、安定的な財源として、充実していく必要があるというふうに考えています。少し、先ほど、ちょっと基調講演の中で触れられなかった点でございますが、もう1つ、課税自主権の問題がございます。これは地方がどれだけ自由に固定資産税の課税標準と、税率を決定できるかということだろうと思いますが、私は課税標準については、交付税算定もございますので、ある程度のスタンダードは国が決めて、実際に課税標準に自由の余地を与えたとしても、スタンダード、交付税を計算するなりなんなり、スタンダードは、国で決めざるを得ないだろうといふうに考えています。 先ほど、ちょっと工藤先生のおっしゃったことに、私なりの少し補足をさせていただきますと、先ほど、私は固定資産税では、税額についての申告というのは基本的に無理だろうというふうに申し上げ、かつ課税標準についても、ここで少し、不統一にするのは無理だろうというふうに申し上げている趣旨は、先ほど、工藤先生がご紹介になった、例えばレイトとか、イタリアの例は、ちょっと私よく存じておりませんので、フランスの例で申し上げますと、例えば、イギリスのレイトというのは、先ほど、申告されて、いろんな個人的な事情、年金生活者である、そういういろんな個人的な事情を書き込んで納税するというお話がございましたけれども、これは納税義務者が土地家屋の所有者ではなくて、賃貸人なわけです。つまり使用者、利用者なわけです。だから、その人の生活状況など配慮しなければいけないのですが、日本の場合には、これは所有者です。フランスの場合で言いますと、税金に未建築地税、農地のような建物が建っていない土地にかかる税金と、それから、既建築地税、既に建物が建っている土地、これは一括建物と考えますけれども、この2つは所有者にかかります。それから、住居税と言われている、住んでいる人々の建物にかかっている税金については、これは賃貸人、借りている人です。実際に住んでいる使用者が納税義務になりますので、イタリアの例でも、恐らく、そういう税金だろうと思います。そういうふうな税金人と、ちょっとの日本の場合には所有者にかかりますので、ここでは、やっぱり限度がある、個人的な事情を考慮するといっても、土地所有者の事情ですし、それから、土地所有者はどこにいるかわからないわけです。例えば、尖閣列島という島は、沖縄県石垣市の所有になっておりますけれども、納めているのは、尖閣列島はすべて、大宮のシヤという結婚式場をもってますので、ここは埼玉県の人が納めなくてはいけないということになりますから、個人的な事情と言っても、どこまで考慮できるのかということは問題ありますから、地域社会では、少し無理なのではないかと。しかし、税率の方は、かなり自由に動かすことを考えてもいいだろうと思います。それから、基幹的な税目ということで申しますと、最終的な調整財源を何にするかという問題が多分地方税では生じてくるのではないかと思います。日本でも申しますと、戦前ですと、市町村だと戸数割、都道府県だと、家屋税が最終調整財源でして、足りないものは、そこのところの税率を上下することによって調整したのです。日本の場合にも、恐らく、これから先ほど、金子先生がおっしゃった受益と負担ということになってくると、どこで調整するのかということが問題になってきますけれども、私は固定資産税だけでは無理で、少なくとも、住民税とセットで考えなくてはいけない。アメリカでも、サーキットブレーカーみたいなことを考えてますけれども、人的な事情を考慮するにしても、必ず住民税を考慮せざるを得ないのではないかというふうに考えています。ですから、受益と負担を考える場合に、かなり住民税的な要素を取り入れざるを得ないのではないか。それから、もう1つは、さまざまな土地利用とセットで考えざるを得ないのではないか。この2つを少し補わせていただいて、私の提案とさせていただきます。 金子 どうもありがとうございました。次に、地方団体としては固定資産税が基幹税として、また、安定財源として不可欠のものであると考えられますが、行財政の増大に伴いまして、これからの固定資産税は、地方団体にとって、いかにあるべきかということについて、西村部長さんから、お願いいたします。 西村 固定資産税につきましては、その特徴でございます地域との密着性、普遍性があること。それから、行政サービスとの対応性、応益性、それから、もう1つ申し上げられるのは税収に安定性、伸張性があるということでございます。これらを考慮しますと、しかも、住民税とは違いまして、独立税ということで、自治体が課税額を実質的に決めるという点でも、最も重要な税目で今後も市町村の基幹税目として、一層充実させていくことが望ましいと考えております。固定資産税の安定性の点ですが、ここ10年を振り返りましても、いろいろな他の税目が景気の影響を受けまして、減収になるとか、税制改正の影響を受けて、減収になるというような中で、固定資産税の安定性が際立っているというふうに思います。東京都におきましても、東京都は、本来は府県税目を所管するところでございますが、市町村税の一部も所管しておりまして、固定資産税もその中の1つでございますが、法人事業税という大きな税目を抱えながらも、単一税目としては、固定資産税の収入が一番大きいということになっております。そういうことで、固定資産税が市町村の安定税目として、その財政の中に占めるということは、行政そのものが安定化するということになるというふうに思います。行政あるいは、財政が安定化するということで、財政運営に緊張感を欠くということについては、十分注意しなければいけないことで、行政の簡素化とか、効率化に対する努力が不足しますと、納税者から納税額の削減を求める要求運動にも発展しかねないと考えるべきではないかというふうに思います。 先ほどもお話がございましたけれども、課税自主権がこれから拡充される中で、今まで固定資産税に対しては、その税率の選択というものが非常に硬直的でございましたが、アメリカの例では、施策と税率の選択ということになると思いますが、日本でも、この住民、それから議会、行政がそのときどきの施策の提案と選択による歳出の必要性に応じて、また、均衡財政を維持するという視点から、税率を選択していくということに、もっと柔軟になってもいいのではないかと。また、同時に、そういうことによって、議会、住民と行政の間の緊張感も維持するということになれば、この基幹税目である固定資産税を介在いたしまして、これからの分権社会において自己決定権を有する地方自治が成熟していくのではないかと思いながら、固定資産税のますますの充実を期待しているところでございます。 金子 どうもありがとうございました。それでは、次に、海外の事例について、特に予算統制手段としての固定資産税率といった点につきまして、工藤先生にお願いいたします。 工藤 先ほどは、神野先生、非常に適切なフォローをしていただきまして、私、居住者ということを申し上げるのを確かに忘れておりましたが、イタリアの例につきましては、ちょっとまた補足させていただきますと、この納税者は所有者です。ですが、先ほども申しましたように、その所有者が年金生活者なのか、あるいは、その住居だけを主たる自宅として所有しているのか、あるいは、投機目的なのかといったようなことを含めて、申告は自分でやる。イタリアの場合には、固定資産税だけではなく、他の事業税すべてについて基本的に納税者申告なので、このへんは、考え方の違いかなと思っております。 それはさておきまして、私は、実は、税制の専門家でありませんで、地方行政の方が専門なので、恐らく、ここの部分は、そのへんとの関係を言うことを期待されているのだと思いますが、例えば、さっきのイギリスの例で申しますと、カウンシルタックスというのは、現在は、独自、いわゆる自主財源の100%を占めているということになりますので、地方のすべての活動を決定する非常に大きな要素になっています。イギリスは極めて珍しい例だと思いますけれども、このように固定資産税的なものが極めて大きな役割を果している中で、実際に、どうやってタックスベース、と言いますか、課税標準を決めているのかと言いますと、これは補助金も含めて。そもそも必要なのは、歳出の予算、それから、一体、歳出に対して、国からどれだけの援助、交付金があるのかということを踏まえて、それに必要な額を割算して出しましょう、というのが発想でありまして。もともと、一体どれだけの活動があって、どれだけのお金が必要なのか、そのときに、どんなプロジェクトがあって、それをどういう割合で負担したら可能なのか、ということになるわけです。ところが、この考え方を押し進めていきますと、いろいろサービスを提供したいと考えると、そのためには、今度はお金が必要ですから、どんどんこのレイトが高くなっていくということも考えられますので、それを補正する意味で、補助金が設けられています。と言いますのは、この補助金は、その差引分を自治体が担当することになりますので、あまりにも住民に過剰な負担を強いるようなことがないように調整をする。逆に、それに頼って住民に対する課税を低くしすぎると、次からは次第に補助金が減るといった、ある意味では、中央からの緩やかな統制手段として使われているわけです。ですから、財政の調整が、既に固定資産的な課税標準を決める段階で生きてくるという意味では、実は、例えば、そのプロジェクトが本当に必要なのか、行政がきちっとした予算決定をして有効にサービスを提供しているのかということを、税金を課す前から決めないと、市民はもちろん、お金を払う前に、それがわかるわけですから、当然、逆の発想できている。ある意味では、予算の統制と言いますか、予算を明らかにして、行政のアカウンタビリティーを高める手段として使われている。ですから、税金を納めるパンフレットが市民に配られるときには、前年の決算はもちろん、翌年のプロジェクトの内容ですとか、補助金の計画なども添えられておりまして、その中で、皆さんの税額はこうですよということになっています。ただし、この計算方式は全国で一律ですので、各自治体に分配される補助金の額が違えば、当然、出てくる課税標準も違うのですけれども、ある程度のスタンダードに押さえる、その役割を補助金がしているということを申し添えたいと思います。 また、課税標準につきましては、やはり、イタリア含め大陸諸国でも、ほぼ同等になるように、さまざまな工夫がされておりまして、その工夫がうまくいかないと、ドイツのように、評価が適切でないということで問題となることもありますが、いずれにしましても、イタリアについても、登記簿のようなものがあるわけですが、それに関しましては、国が一律に管理をしている。それぞれの実態的な運営は地方自治体に任されますが、標準は国によって、ある程度の統一が図られております。 税額については、これは上限、下限が決められておりまして、イタリアの場合、例えば、税率、市町村に委ねられている税率というのは0.4%から0.7%の間ということで、0.3%の開きがありますが、この中で各自治体が毎年自由に決める。自治体で、さらに細かく控除なども決めることができるということで、それぞれの自治体の独自性というのは、そこに生きてくるようになっています。そもそも、イタリアのことを申しますと、この、独自財源を高めようという動きは、実は、1990年代になって初めて出てきた状況でありまして。よく、イタリアというのは地方分権が非常に進んだ、盛んな国だという、日本ではその誤解が広がっているのでありますが、1970年代に州が設立されたり、新しい地方団体ができたというのは、実は、国の肩代わりと言いますか、中央統制の手段としてつくられたものだったのです。財政構造を見てみますと、1970年代というのは、実は、補助金の額が増えまして、むしろ、国が介入する余地を高めるために、財政的にも、より介入していくということが行われてきました。それを奪回しなければいけないということで、1990年代に入りまして、実は1989年に、市町村に事業税、一応、日本でもありますけれども、地方事業所税に非常に近いものができたのです。これは極めて新しい発想と言いますか、地方自治体が自らの活動費用を自分たちで決定していくということに先鞭をつけまして、それ以後、地方の単位で、新しく固定資産税の仕組みができたりと、93年ですけれども、最近になって進んできている現象です。 何で90年代になって、この財政の、向こうでは直訳いたしますと連邦化、日本語で言うと、財政分権化と言えばいいかと思うのですが、これが思想として非常に流行ってきたかと申しますと、やはり90年代の課題として、イタリアにも高齢化があります。さらに少子化が進んでいる国ですので、高齢化のスピードも非常に早くて、このような中で、医療、福祉行政、特に健康保健の行政というのは、これまでのように、国でお金をプールして各州にばら蒔くというのではほとんど、それぞれのニーズに応えられない。では、この保健医療行政を何とか分権化しなくてはいけない。そして、その格差を財政調整で行うのではなくて、独自財源の強化という方向でやっていこうというのが背景にありました。ですから、90年代の財政改革というのは、1つには独自財源の強化、あるいは、システムの簡略化ということもあったのですが、背景としては、むしろサービスの充実ですね。先ほど神野先生もおっしゃられておりましたけれども、どうやって社会サービスを提供するかということが先にあって、では、それに対して、一体どういう手段で、そのサービスの費用を捻出するのが適切か、ということにあったと思います。ですから、実際には、南北格差のあるイタリアでは、例えば、北部でのサービスと南部でのサービスは違うかも知れないけれども、当然、それぞれの自治体における税制の構造も違っておりますが、それによって逆に特色のあるサービスを提供することも可能になっている、ということだと思うのです。 ですから、日本の場合、実はなかなか、受益者負担、あるいは、受益と負担の関係というのが、市民のレベルでわかりにくいというところは、まだまだあるのですが、今後、介護保険も含めて、福祉、それから年金も関係あるかと思いますけれども、特に福祉医療行政というのが変わっていく中では、恐らく、税制改革というのは、どうしても必要なことなのではないか。そのときにやはり、固定資産税は、先ほど神野先生もおっしゃいましたけれども、最終的な調整という意味では、若干、柔軟性に欠ける部分もあるかも知れませんが、逆に不況にも強く、あまり大きな変動を受けないという意味では、非常に重要なのではないかと思います。私も、諸外国の例を見てましても、最終的な調整をするのは、やはり事業税的なものであるとか、生産活動税のようなもので、ある程度柔軟性のあるものということになるかと思います。ただ、このテーマから言いますと、固定資産税の重要性というのは、地方分権が進み、そして、かつ、特に地方でのそういった福祉、医療関係のサービスが増えるにつれ、重要性というのは増すのではないかというふうに思ってます。  金子 どうもありがとうございました。次に今後のあり方について、地方分権と地方財政の考え方を武田課長さんからお願いいたします。 武田 地方分権については、神野先生が中心的役割を果たされて、平成9年7月に分権推進委員会の第二次勧告が出されたところです。その中で、特に地方財政に関して言いますと、地方と国との歳出、それから税収入の構造を見た場合に、歳出で見ますと、国と地方全体に占める地方の割合が約3分の2というのに対しまして、税収入は全体に占める地方の割合が3分の1程度であるということで、歳出と税収入との乖離というのが大きいわけであり、これを縮小すべきであるという基本的な勧告が出されております。その際に、税につきましては、課税自主権を尊重しつつ、地方税の充実確保を図る。その際に、どういう形で地方税を確保するかということで、税源偏在が少ない、また、税収が安定をしている、こういうふうな点に着目した地方税体系を確立すべきである。このような勧告がなされているわけであります。固定資産税が、市町村の基幹税目であるということは言うまでもないわけでありますが、税収入の偏在についてはどうだろうということで、少しデータを見てみますと、全国の人口1人当たりで自治体間の格差というものを見てみますと、平均を100といたしますと、市町村税全体の一番低いところで46、一番高いところで184というふうに格差がございます。それに対しまして、固定資産税は一番低いところで50、一番高いところで167ということで、市町村税全体に比べると、やや偏在度が少ない。特に家屋につきましては、69から138ということで、かなり全国的に見ても、偏在度が少ない、そういう税になっているかと思います。 それから、税収の安定性ということを見ますと、固定資産税というのは、極めて安定をした税収確保の財源であるということで、昭和25年の固定資産税創設以来、着実に充実をしてきております。安定した税目であることは間違いがありません。もう1つの市町村税における基幹税目は住民税ということになりますが、この住民税の場合、特に、ここ数年、特別減税ということで、減税を行ってきておりますし、また、これから恒久的な減税というような議論にもなっているということがあります。そういうことを考えますと、市町村財政の中で、固定資産税の占める役割は、極めて重要なものであるということが言えると思います。それから、課税自主権の尊重ということも地方分権と税を考える際に非常に重要な視点です。その際に、特に税率を自由に各団体で設定をするということも議論をされてまいりました。現在の地方税法上の仕組みを申し上げますと、標準税率制度をとっておりまして、基本的には、財政上の特別の必要がなければ、その標準税率を採用していただく。しかし、特別の必要があれば、上げ下げは自由である。一定の制限税率がありまして、標準税率1.4%に対して、その5割増しの2.1%という制限税率がありますが、その範囲の中であれば、税率の上げ下げは、地方税法上は自由になっております。さらに、今年の平成10年度の改正におきまして、これまで標準税率を超えて、税率設定する場合に、自治省に届出をするということになっておりましたが、この自治大臣への届出制度を廃止をいたしたところです。 現在、この税率はどのようになっているかということでありますが、標準税率を超えて課税をしておられる団体は、現在、280団体、全国にございます。それから、標準税率未満の団体は、これはゼロです。これはなぜ、そういう標準税率を下回るような団体がないのかということを考えますと、今、言いましたように、地方税法上はフリーになっておるわけですが、地方財政法の中で、標準税率未満の団体については、地方債の制限がかかるということが関連しているかと思います。これにつきましても、分権委員会の勧告の中で、こういった点については制限の緩和をするという方向で見直しが提言されておりまして、現在、この制限緩和につきまして、検討がなされているという状況です。そのようなことを踏まえますと、今後、税率による調整というものが実質的にやりやすくなる、そういう環境ができてくるのではないかというふうに思われるわけです。先ほど、工藤先生の方からもお話がございましたように、諸外国では、特に財産税を中心として、地方団体が必要な歳入を総評価で割り戻すというようなことで、税率を設定する。そういうふうなやり方をやっているところもあるようです。ただ、日本の場合に、必ずしも、そういうやり方が、今直ぐはどうもできそうもないと思いますのは、1つは、地方税と言いましても、税目が単一ではないというようなこと、いわゆるミックスタックスの制度をとっているということ、それから、交付税等による財政調整を行っているということ、それから、歳入に占める地方税のウェートが少ない、というようなことから、現段階では、固定資産税のみで、行政サービスの受益と負担がストレートに決定される形にはなっていないわけです。しかし、今後、地方税が市町村の収入の大宗を占めるというような時期がくれば、もう1つの基幹税目であります住民税のあり方とも関連をするわけですが、固定資産税につきましても、例えば、その税率の決定ということが納税者の選択、あるいは課税市町村の自主的選択によって決定される、そういう状況が実質的にかなり出てくるのではないかと、このようにも思うところです。 目指すべき固定資産税のイメージ 金子 どうもありがとうございました。それでは、最後に、今後地方分権の伸展とあいまちまして、固定資産税の安定的な姿として、どのような制度が望ましいのか、目指すべき固定資産税のイメージについて、それぞれパネラーの先生方から一言ずつお願いいたします。まず、西村先生お願いいたします。  西村 これから目指すべき、固定資産税のイメージということですが、先ほども申し上げましたように、市町村の最も重要な税目として、固定資産税を充実していく必要があると申し上げましたが、これには、何よりも納税者の方の理解と納得が必要だということでございます。納税者の信頼性を得る一番は、長年固定資産税にかかわってきた皆さんのご経験からも感じておられると思いますが、やはり現行の制度の中に、どうしてもわかりにくい面があると、そのへんを簡素化、簡明化、わかりやすくするということが一番大切だというふうに思います。それはどういうことかと申しますと、これは12年度の基準年度に向けて、自治省の方でも、その負担調整のあり方等について、さらに検討していくというお話でございますけれども、基本的には将来の方向としては、個別土地の評価額は、公開された路線価に基づきまして、納税者自身が簡単に算出できること。そして、その税額につきましても、その評価額に基づいて、容易に算出できるというような仕組みにする必要があると思います。つまり、課税の面では、基本的には、土地については本則課税にするということで、負担の一層の均衡化を進める必要があるということでございます。現行の制度の中では、据え置きになっているものと、それから、地価が下落する中でも上がるものがございます。商業地については80%という負担水準も設けられております。これら負担水準80%以上の土地については、地価が下落すれば、必ず下がるところではございますけれども、今後、この非常に複雑な負担調整措置を段階的に廃止していくという必要があるのではないか。そのときに、それに伴う負担増につきましては、特に資産はあるが、所得がないというような年金生活者等への配慮を一つしていく必要があるかなというふうに思っております。これはアメリカにも制度があるそうですが、納税の猶予制度ということでございますが、日本でも、既に実施している地方団体があります。これは住宅資産活用制度ということで、この制度を発展させて、納税用に活用することができれば、負担均衡化が進めやすくなると思いますし、納税者の立場から言えば、定住の確保ということになります。最近、固定資産税の滞納が非常に多くなっておりますが、滞納発生の防止にも寄与できるのではないかと思います。これは制度と申しましても、自治体独自に実施することも可能でございますので、検討を進めていきたいというふうに考えておりますが、そういう制度改革に耐えられる納税しやすい仕組みをつくりまして、負担の均衡化を一層進めていただければというふうに思います。それから、評価の面で、もう1つ申し上げますと、これも納税者の方の信頼性を確保するということについてですが、現在は地価公示価格水準の7割ということで、全国評価の均衡が図られているということでございますけれども、この地価公示価格、それから、各県には基準地価格がございます。それから、相続税と市町村の固定資産税の4つの公的評価がありますが、この評価事務を一元化することによりまして、評価の統一性を一層確保できるのではないかというふうに思っております。これは行政の効率化を進める観点から、徴収事務の一元化ということも言われておりますが、私は自治体の自己責任を確立する上で、徴収事務については、それぞれの自治体が責任を持って行うべきというふうに考えております。今後は、地価公示価格が適正であるということがすべての公的評価の条件になりますので、この評価事務につきましては、地域の状況に詳しい市町村が中心になってやっていくのが適当ではないかと考えております。もっとも大都市以外では、共同になるかというふうに思います。また、相続税等にも使われるということで、毎年評価替えが必要になりますので、その市町村が評価事務を毎年一元的に行うことについては、必要な財政措置をする必要があると思います。市町村の基幹税目である固定資産税の評価に今後も積極的にかかわっていくということで、提案と言いますか、評価の一元化を市町村が中心となって行っていくという考え方は、どうだろうかというふうに考えているところでございます。 西村 これから目指すべき、固定資産税のイメージということですが、先ほども申し上げましたように、市町村の最も重要な税目として、固定資産税を充実していく必要があると申し上げましたが、これには、何よりも納税者の方の理解と納得が必要だということでございます。納税者の信頼性を得る一番は、長年固定資産税にかかわってきた皆さんのご経験からも感じておられると思いますが、やはり現行の制度の中に、どうしてもわかりにくい面があると、そのへんを簡素化、簡明化、わかりやすくするということが一番大切だというふうに思います。それはどういうことかと申しますと、これは12年度の基準年度に向けて、自治省の方でも、その負担調整のあり方等について、さらに検討していくというお話でございますけれども、基本的には将来の方向としては、個別土地の評価額は、公開された路線価に基づきまして、納税者自身が簡単に算出できること。そして、その税額につきましても、その評価額に基づいて、容易に算出できるというような仕組みにする必要があると思います。つまり、課税の面では、基本的には、土地については本則課税にするということで、負担の一層の均衡化を進める必要があるということでございます。現行の制度の中では、据え置きになっているものと、それから、地価が下落する中でも上がるものがございます。商業地については80%という負担水準も設けられております。これら負担水準80%以上の土地については、地価が下落すれば、必ず下がるところではございますけれども、今後、この非常に複雑な負担調整措置を段階的に廃止していくという必要があるのではないか。そのときに、それに伴う負担増につきましては、特に資産はあるが、所得がないというような年金生活者等への配慮を一つしていく必要があるかなというふうに思っております。これはアメリカにも制度があるそうですが、納税の猶予制度ということでございますが、日本でも、既に実施している地方団体があります。これは住宅資産活用制度ということで、この制度を発展させて、納税用に活用することができれば、負担均衡化が進めやすくなると思いますし、納税者の立場から言えば、定住の確保ということになります。最近、固定資産税の滞納が非常に多くなっておりますが、滞納発生の防止にも寄与できるのではないかと思います。これは制度と申しましても、自治体独自に実施することも可能でございますので、検討を進めていきたいというふうに考えておりますが、そういう制度改革に耐えられる納税しやすい仕組みをつくりまして、負担の均衡化を一層進めていただければというふうに思います。それから、評価の面で、もう1つ申し上げますと、これも納税者の方の信頼性を確保するということについてですが、現在は地価公示価格水準の7割ということで、全国評価の均衡が図られているということでございますけれども、この地価公示価格、それから、各県には基準地価格がございます。それから、相続税と市町村の固定資産税の4つの公的評価がありますが、この評価事務を一元化することによりまして、評価の統一性を一層確保できるのではないかというふうに思っております。これは行政の効率化を進める観点から、徴収事務の一元化ということも言われておりますが、私は自治体の自己責任を確立する上で、徴収事務については、それぞれの自治体が責任を持って行うべきというふうに考えております。今後は、地価公示価格が適正であるということがすべての公的評価の条件になりますので、この評価事務につきましては、地域の状況に詳しい市町村が中心になってやっていくのが適当ではないかと考えております。もっとも大都市以外では、共同になるかというふうに思います。また、相続税等にも使われるということで、毎年評価替えが必要になりますので、その市町村が評価事務を毎年一元的に行うことについては、必要な財政措置をする必要があると思います。市町村の基幹税目である固定資産税の評価に今後も積極的にかかわっていくということで、提案と言いますか、評価の一元化を市町村が中心となって行っていくという考え方は、どうだろうかというふうに考えているところでございます。金子 ありがとうございました。それでは、次に工藤先生お願いいたします。 工藤 今までにも何回か申し上げたことなんですけれども、これから、分権化の中で、固定資産税というのを評価していく必要があるかと思いますが、その中でも、特に私が思いますのは、やはり都市計画です。それから、土地利用をベースとした都市計画の充実。それとのかかわりの中で、固定資産税の評価という問題も考えていく必要があるのではないか。実は、これは言うは易し、やるは難しという典型的パターンかと思いますけれども、やはり、今後分権化が進んでいく中で、地方のサービスは、一体そのまちにとって何が最も重要なのか、あるいは、その優先順位は何なのかということを考えていく中で、もちろん対人的な社会サービスというのは重要にはなりますけれども、やはり、もう一つの根幹にある都市計画、土地利用ということとも併せて考えていくべきではないか。それには、固定資産税というのは非常に有効な手段ではないかというふうに考えています。 同時に、先ほど、イギリスは非常に珍しい例で、固定資産税がほとんど占めていると。税収のほとんどを占めているということで、比較的、予算との関係が明確ではありましたが、これももちろん、地方への交付金というのを差し引いた残りの部分をどう再配するかということでありますので、当然これは、プロジェクトの中身は一体どんなもので、行政の事務が一体何なのかということがベースになっているかと思うのです。そうしますと、やはり、比較的市民にとって、わかりやすい税制を敷いていく、その中でも特に、どちらかと言うと、税制だけではなくて、行政がやっている活動についてのアカウンタビリティーを高めていくため。私はやはり税金というのは、市民意識を喚起するいいきっかけになるのではないかというふうに思います。 ただ、そうは言いましても、均衡化、そして、平均化というのを追及していく中でも、これからはやはり、ある程度柔軟な適用とか、特例のような形で、戦略的に政策を進めていく、そのための手段としても使うことが有効ではないかと思います。これは、恐らく賛否両論、最も激しい分野で、最後に申し上げると、いろいろ議論の対象になるかも知れませんが、敢えて言わせていただきますと、固定資産税の運用なんです。これは諸外国でもさまざまに問題になっておりまして、例えば、ヨーロッパの中心街では、やはり固定資産税が高いために脱税行為が横行する。あるいは、固定資産税、相続税が高くて払えないために、非常に歴史的な建造物が失われていくというようなことがあります。これに対しては、それぞれの自治体でさまざまな工夫がされているわけですけれども、歴史的な価値を認められた建物については、大きく軽減をする。特に、子孫がそのまま住宅利用として住んでいる場合には、著しい軽減をするとか。あるいは、どうしても手放さなければならない状況になったときには、市町村が基金を構成して買い取るなど、イタリアの場合はよく行われております。こういった柔軟な運用というのは、確かに、固定資産税や、特に相続税を万遍なく課税するということからは外れるかも知れないのですけれども。実は、2週間ほど前の週末に政治学会で京都にまいりまして、京都の町家の復興を見せていただく機会がありましたが、その運動に加わっている弁護士さんの方にいろいろお話を伺ったところ、やはり相続税というのは、町家の復興や、あるいは、街なみの保存といったことにはネックになっている。これは非常に難しい問題ではあると思いますが、やはり、それぞれの自治体の自由度が将来的に増していく中では、柔軟な運用、あるいは、戦略的な運用ということも考えていくべきではないか。実は、そのような戦略的な運用、つまり、この街なみは守りたいというのは、かなり戦略的な意思なわけですが、そういった行政側、あるいは、住民の意思を反映できるものとしての可能性を持っていると思われますので、そのへんが、今後議論されていけばいいのではないかというふうに思っております。 金子 どうもありがとうございました。それでは、神野先生お願いいたします。 神野 私もほとんど工藤先生がおっしゃったことと同言反復になってしまいますが、一応、私の言葉で述べさせいただけば、依然として、固定資産税が地方税、特に、市町村税の基軸になるということは間違いないことだろうと思います。先ほどもちょっとご紹介させていただきましたけれども、日本も工藤先生がおっしゃったようなヨーロッパと同じような課税標準を全部決めておいて、後で割り戻して、税率を決めるというやり方を戦前とずっととっておりました。先ほども申し上げました都道府県は家屋税、固定資産税の一つの源流になっている家屋税、それから、市町村税では、戸数割が割り戻して税率を決める。毎年、毎年税率を決めていくラストリゾートと言いますか、最後の調整財源になっていったわけです。ですから、戸数割は、今、住民税になってるわけですし、住民税と固定資産税というのは、やはり2つの市町村のキータックスに今後ともなっていくだろうということであります。納税者の協力、固定資産税をそういう基幹的な税目として、育てていくのに必要なのは、やっぱり納税者の協力、それから、参加などのご指摘が西村部長からありましたけれども、全くそれはそのとおりであります。それと同時に、先ほど工藤先生も少しご指摘になっていたかと思いますが、公共サービスに関する受益と負担との関係というふうに金子先生がおっしゃっていた意味での受益との関係を明確にさせると。一般的なサービスの受益になりますけれども、どう使われていくのか。使われ方に対する監視体制、これを説明、アカウンタビリティー、こういったものを少し考えていく必要があるというふうに思います。 それから、さはさりながら、土地を投機の対象にさせますと、幾ら税務行政の方で透明化を図り、公共サービスとの関係で、きちっと必要性の説明をしたとしても、地価の方が乱高下激しくなれば意味がないのです。この乱高下を激しくさせないのには、やはり必要なのは徹底した規制だと思います。規制緩和と言っても、していい規制と、やらなければならない規制とありまして、私は土地については徹底した規制が必要だと。これは工藤先生がおっしゃったことで行きますと、都市計画と土地の利用計画、これとセットで新しいまちづくりをつくっていく。対人社会サービスと同時に、もう一つの重要なこととおっしゃっていたまちづくり、どういうまちづくりをしていくのかという、そのまちづくりは、これは規制とセットじゃないと意味がないわけです。同時に、先ほどの相続税の話とか、それからフランスもそれから、スウェーデンもやってますけれども、そういうものは固定資産税とセットで、地方がどんどん買っていかないとダメなわけです。守っていくところは、買って、公共の空間をつくり出していくというまちづくりが必要なのではないかというふうに思います。特に、今後、私たちは本当にまちづくりに迫られているのだと思うのです。戦前は、強兵でもって土地計画をつくり、国土を整備してきたわけですし、戦後は50年かけて富国という視点からまちづくりをしてきたのですけれども、これからはそれぞれ個性のあるまちづくりを多分していかなくてはいけない。そのときに、戦後50年かかった富国のまちづくりで、全国画一的なまちづくりにさせられちゃったために、これから、まちづくりでスタートしてくださいと言われたときに、それぞれの地域が今、もう自信を失っちゃって、どうもどこへ行ってもまちづくりを見てみると、個性的なまちづくりというと、イタリアのナポリにしましたとか、スイスのチロルにしましたとか、日本固有のそれぞれ地域に固有なまちづくりがなくなっているんです。教育で重要なのは、その人間の弱点を補ってやることではなくて、長所をやっぱり伸ばしてやることだと思うのです。弱点というのは、補ってやっても高々人並みなんです。日本はアメリカや外国の真似をしてまちづくりをしても、高々人並みで、そこに定住してきたりするような人は来ないわけで、それぞれその地域の個性、得意とするところを利用したまちづくりを今後していく。そのときの財源として、固定資産税というのは重要な財源になっていくのではないかというふうに思います。以上です。 金子 どうもありがとうございました。それでは武田先生お願いいたします。 武田 それでは、固定資産税の今後のイメージということでありますが、地方税を巡るさまざまな現在の状況から考えますと、固定資産税の安定的充実確保というのが極めて重要であるというふうに考えております。そのためには、何と言いましても、納税者の理解と信頼をいただくということが大前提であろうかと思います。そのために、3点ほど触れさせていただきたいと思いますが、1つは公平でわかりやすい固定資産税を確立をしていく。2つ目は納税者の主体的参加をお願いをしていく。3つ目は適正な評価にさらに努力をしていく。こういうことではなかろうかと思います。 まず1つ目の公平でわかりやすいという点では、先ほど一番最初に申し上げましたように、やはり過去からのいろいろな経緯の中で、特に土地の課税につきましての評価と、税負担との関係がストレートでないという点、税負担水準の不均衡があるという点、こういった点をできるだけ早く解消をしていく。負担水準の均衡化をできるだけ早く図っていくということが非常に重要な課題ではないかなというふうに思っております。 それから、2つ目の納税者の主体的参加ということでは、そのために、やはり情報開示を一層進めるということが非常に重要ではないかなと思います。これは各市町村にご協力をいただきまして、平成9年度におきましては、全路線価、393万地点の公開をすることができたわけでありますし、また、いわゆる、課税資産の内訳書、課税明細書の送付にも各市町村のご努力をいただいてるところです。今後はさらに、縦覧制度、あるいは、閲覧制度の見直しということで、これにつきましてはプライバシーの保護との関連も視点として必要だと思いますが、そういった点の見直しも検討課題になってくるかと思いますし、不服申出制度、先ほど申し上げましたような審査の迅速化でありますとか、申出期間のあり方等につきまして、具体的な検討を進めていきたいというふうに考えております。 そして3つ目の適正な評価にさらに努力をしていくということでありますが、固定資産税における、特に土地の評価につきましては、収益還元法を用いるべきである、こういう考え方があることを承知をいたしております。ただ、現時点におきましては、収益還元法には、例えば、還元利回り率などの客観的なデータを把握する点で、難しい面がある。あるいは、実際の賃貸料等にも、かなりの格差が見られる。さらに、我が国には、成熟した不動産の賃貸市場というものがまだ育っていないのではないか、というふうな幾つかの状況がございます。こういうことから現段階では、原則的な考え方としては、売買実例価格をベースとしているところでございますが、今後、経済社会の動向等も踏まえながら、収益還元法をどのように活用していくことができるかということも視野に入れながら、より適正な評価方法の確立を図っていくことが必要であると考えているところです。 最後に固定資産税の今後のイメージということでありますが、神野先生の基調講演の中にもございましたように、土地につきまして、あるいは、家屋もそうであろうかと思いますが、いわゆる、土地・家屋等の固定資産税の課税客体というものは、まさに地方自治体を構成する最も重要な要素であるというふうに感じます。即ち、固定資産税というのが最も地方税らしい、地方税としてふさわしい税である。そういうイメージを私は持っているところです。昭和25年に現在の地方税法の制定とともに、固定資産税が創設されて以来、今年で48年を迎えるわけであります。そうしますと、2年後、今度の評価替え、平成12年の評価替えのときに、ちょうど50年を迎えるわけです。これまでの多くのいろいろな経験を踏まえまして、見直すべきところは見直しをし、市町村の基幹税目として、納税者に一層理解され、信頼されるように取り組んでいく必要があると考えております。本日、ご参加の関係者の方々のご協力もいただきながら、精一杯努力をしていきたいと考えているところです。 金子 どうもありがとうございました。以上で予定をしておりました問題点について、パネラーの皆様から、お話をいただきました。パネラーの皆様には、本当にありがとうございました。本日は、皆様から、大変率直で前向きなお話を出していただきまして、また、白熱したと申しますか、ドラスティックな意見も出していただきまして、内容が非常に豊富だったと存じます。それから、会場の皆様方には、長い時間、大変熱心にご清聴いただきまして、本当にありがとうございました。それでは、本日のパネルディスカッションはこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 |
|
評価センターは固定資産税に関する研究・研修・情報提供機関です。 |
|